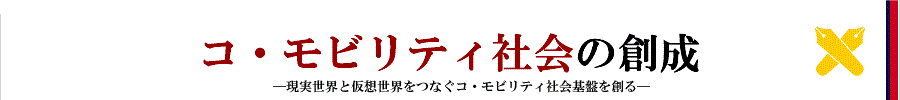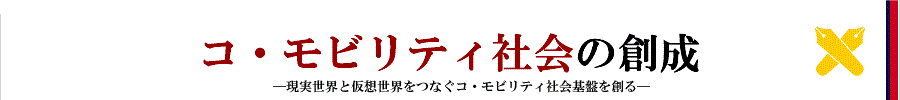|
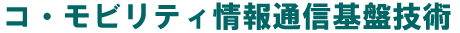
慶應義塾大学 環境情報学部 学部長、教授 村井純
慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 植原啓介
|
リーダー:慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 三次仁
目的と概要:
時空間情報システムにおいては、空間情報を継続的に収集する必要があります。本SWGでは、このような空間情報の収集技術に関する研究開発を行っています。
通常、情報システムの上で生成された情報は、そのまま情報システムで継続的に処理できます。しかし、実空間を対象とした情報システムでは、どのようにして実空間の情報を情報システムに取り込むかが一つの重要なポイントとなります。そこで、様々な手段を利用して空間の情報をデジタル化し、ネットワーク上に取り込むシステムを検討する必要があります。
本SWGでは、ボトムアップに空間センシングの手法について、研究を行っています。初期段階としては、参加者が得意とする分野から時空間情報を収集するシステムを構築し、それぞれの特徴などについて議論を行います。次の段階としてそれらの時空間情報センシングシステムとしての位置付けの整理を行います。最終的には、時空間情報を把握するためのシステムアーキテクチャの整理を行います。
|
|
|
リーダー:慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究助教 鈴木茂哉
目的と概要:
社会システムを支える時空間情報は膨大な情報量となることが予想されます。そこで本SWGでは、膨大な時空間情報を蓄積し、そこから新たな知見を生み出し、必要な情報を必要な人に提供するためのシステムの研究開発を行っています。
時空間情報はあらゆる場所で継続的に生成される情報です。この為、情報の蓄積のためには、空間毎に情報システムを分割するなど、何らかの工夫が必要となります。
また、センサ等によって生成された情報は、必ずしもそれだけで人間にとって有効な情報とはなりません。たとえば、気温履歴そのものよりも、そのセンサタグが貼付されているワインの状態が良いか悪いかが人間にとっては重要となります。このような、人間にとって有用な情報を自動的に生成するシステムを研究開発します。
更に、時空間情報を利用する場合、その情報をどのようにアプリケーションに提供するかといったAPIが重要となります。このようなAPI及びそれを支えるシステムの研究開発を行います。
最後に、時空間情報を構築するための空間表現について研究を行い、時空間情報システム全体において利用します。
|
|
リーダー:慶應義塾大学 理工学部 准教授 重野寛
目的と概要:
移動体に様々な時空間情報を提供するためには、移動体を対象とした通信システムが必要となります。本SWGでは、移動体に情報を提供、移動体から情報を収集するための通信システムの研究開発を行います。
移動体の自動運転/遠隔運転においては、移動体同士あるいは移動体と走行環境(歩行者などを含む)の間で短時間に信頼性を持って情報を交換する必要があります。そこで、本SWGでは、自動/遠隔運転に十分な時間で情報を交換できる実時間情報提供向け通信システムの研究開発を行います。
また、移動体の走行計画を立てるためには、渋滞や気象といった道路状況の把握、凍結路や歩行者が多い等の走行に注意が必要な場所の把握といった経路上の環境把握が重要となります。このような情報を時空間情報プラットフォームから得るためのIPを用いた通信システムの研究開発を行います。
|
|

|